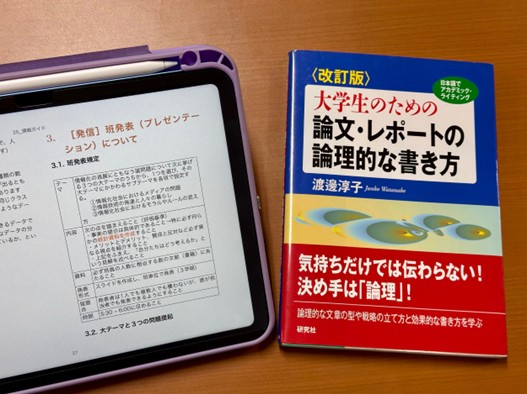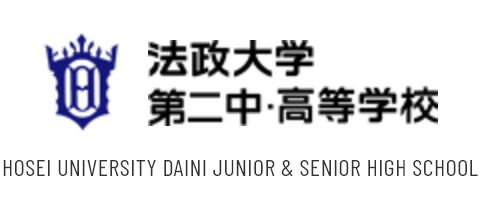Q.今日の高校情報科の授業では、どのようなことに取り組んでいますか?
高校1年生の取り組みで、①「メディアの問題」・②「情報技術の発達」・③「ネットマナーと情報モラル」の3テーマをもとに「プレゼンテーションに向けての準備」をグループワークで取り組んでいます。希望する大テーマを各グループ1つずつ選択し、自分たちでサブテーマを設定すべく、ブレインストーミングやロジックツリー、KJ法などの思考手法を用いて内容を整理します。
2学期は、テーマ設定や構成を考え始め、各自の調査内容を決めます。3学期に調査結果を個人論文でまとめ、グループ内で結果を共有し、プレゼンテーションの本番を迎えます。

Q.高校情報科では、このような取り組みをもとにして、どのような力を身に着けてほしいですか?
現在の生徒は「ディジタルネイティブ世代」と言われますが、ネットリテラシーの習熟度には大きな差があると捉えています。そこで、「情報Ⅰ」では大学付属である本校の特色を活かし、大学共通テストに捉われない「大学で、また社会人として」有用となる内容に焦点を当てて授業を構成しています。その中で「プレゼンテーション」の実践は、情報を取り巻く重要な3要素である「受信・加工・発信」を実際に生徒自身が行なう活動と位置づけており、主体的に学習を進めていくための基礎づくりに役立つものと考えています。
また、情報の「発信」は、プレゼンテーションで”話す”ことのみならず個人論文で”書く”ことによる表現も経験しています。調べたことや考えたことを文字にすることは、生徒にとって大きな労力が必要ですが、自身の思考整理には”書く”ことが最も効果的であると考えています。加えて、引用手続きや参考文献の書き方を扱うこととなるため、今後の学習・研究活動で必要となる「アカデミックリテラシー」の基礎を抑えることも意識したカリキュラムとしています。
教科「情報」は、2003年度に始まった”ばかり”です。情報科で扱う内容は、他教科よりも歴史が浅いため、「専門で学ぶ人だけ」が必要という意識が今でも残っているように感じます。しかしながら現在、どの分野においても学習・研究活動にコンピュータを活用するようになり、もはや「誰しも」がその内容を知る必要がある時代となりました。その内容を実践し「知っている」から「できる」ようにすることが、本校の教科「情報」の大事にしているねらいです。